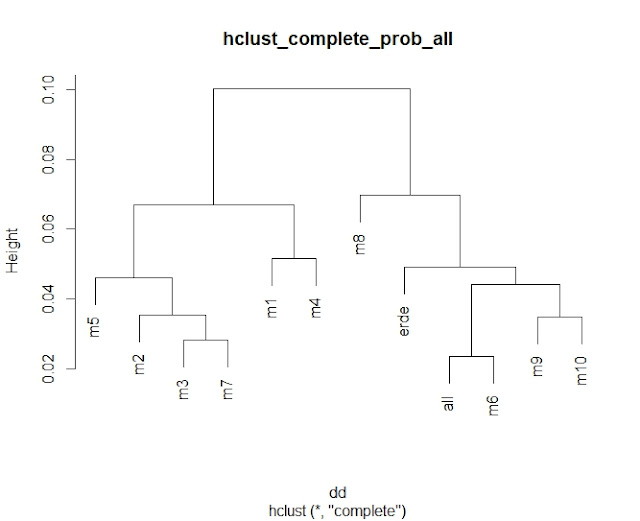2023年12月24日 ミューザ川崎シンフォニーホール
ヤナーチェク シンフォニエッタ
マーラー カンタータ「嘆きの歌」(第1部:初期稿、第2部,第3部:最終稿)
日野祐希(ソプラノ)
蔵野蘭子(アルト)
西山詩苑(テノール)
原田光(バリトン)
東京オラトリオ研究会(合唱指揮:郡司博)
* * *
とはいうものの今回の公演が2020年の新型コロナウィルス感染症の流行以降、初めてコンサートホールに足を運ぶ機会であったことについてはやはり触れておくべきかと思います。既に今年(2023年)のゴールデンウィークを境に(正確には5月8日以降)、新型コロナウィルス感染症の感染症法(正式には「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」)上の分類は5類に変更され、コンサートの開催についても既に制限がなくなって久しいとはいえ、そのことは新型コロナウィルス感染症の流行が収束したことを意味せず、実際その後も職場や教育の現場では少なからぬ、否、時として感染対策に万全を期していた時期と比べて寧ろ多くの感染が確認されましたし、少なくとも私が知る限り、医療や介護の現場では分類変更以前と変わらない対応を継続したところも少なくありませんでした。そのうちにインフルエンザ等の新型コロナウィルス感染症以外の感染症が流行の中心となり、結果として今回の公演は様々な感染症の流行に対する警戒が続く中での開催となりました。そうした状況を踏まえるならば、これまでであれば慎重を期して訪問を控えることを検討するところで、実際過去には、新型コロナウィルス感染症の流行によって幾度か公演が延期された後、ようやく流行の合間での公演が実現した2021年5月8日の第18回定期演奏会における第3交響曲の演奏だけではなく、既にポスト・コロナ禍の状況下での、いわば再出発の公演となった2022年9月11日の第20回定期演奏会での第2交響曲の演奏についても再び、直前まで訪問を予定していながら、間際になって避け難い事情により演奏会場に赴くことを断念せざるを得なくなったりということもありました。これら両公演についても企画に賛同し、公演プログラムに寄稿させて頂いた点は同じで、公演に立ち会うことを或る種の義務の如きものと感じていた点も変わらず、それ故に已む無く欠席せざるを得なかったことは少なからぬショックでした。幸いにして、避けがたい用件に割り込まれ、またしても公演に立ち会うことができなくなるのではという懸念は今回について杞憂に終わり、結果として、もしかしたら今後二度と経験することができないかも知れない「嘆きの歌」の実演という稀有な機会に立ち会うことができたことの幸運を噛みしめています。寄稿文の末尾で記したように「マーラー自身の行為を、場所を変え、時を変えて記憶し、反復し、継承することによってマーラーその人に応答すること」が、このように実現されたのを目の当たりにして深く感動するとともに、演奏したことのない作品、一般に演奏頻度の低い作品を取り上げられることに伴う苦労は、いわゆる定番の作品を演奏する場合と比較にならず、様々な困難を伴うことを思えば、公演に接した感想を記すにあたってまず最初に、この日の公演での達成に対して、公演に携わった全ての方に対して敬意を表したく思います。
* * *
一方ヤナーチェクとマーラーの組み合わせについて言えば、一般的にマーラーはオーストリアの交響曲創作の伝統の中に位置づけられるが故に等閑視されがちではありますが、生誕の地はボヘミアであり、生後間もなく移住した街はドイツ語の「言語島」である一方でボヘミアとモラヴィアの境にあったことから、少年期のマーラーはモラヴィアの民謡を日常的に耳にしていたであろうことを思い起こすならば、そうした作品が生まれる土壌の如きものに関して自然なものに感じられます。実際マーラーの音楽の特徴の一つとして、拍節が自在で所謂変拍子が頻出することが挙げられるのではないかと思いますが、それはボヘミア系の音楽よりも寧ろモラヴィア系の音楽の特徴に通じるものと考えられますし、実際「嘆きの歌」にもモラヴィア風のメリスマを伴った変拍子の旋律が要所で登場し、その抑揚は聴き手に鮮烈な印象を与えずには置きません。
更にそうした音楽の基層にあたる部分での繋がりに関連して言えば、指揮者・音楽監督の井上喜惟さんの正式デビューがモラヴィアの中心都市であるブルノでの1992年のチェコ国立ブルノ・フィルハーモニー管弦楽団の定期演奏会だったことも思い起こされます。以前、第10交響曲のクック版の演奏に接した際に、特に第2楽章に現れる変拍子の扱いが非常に自然なものに感じられたことを記したことがありますし、マーラーを離れれば、アルメニアのオーケストラとの共同作業に長きに亘って取り組まれていることも思い浮かびますが、今回の演奏においても、そうした拍節の自在さが、ヤナーチェクとマーラーの両方に共通して、何よりもまず身体的な感覚のような水準で自然に達成されているように私には感じられたことを述べておきたいと思います。(勿論、シンフォニエッタも「嘆きの歌」も編成上、バンダが用いられ、それぞれ重要や役割を果たすという共通点があることで、プログラム構成上合理性があるという現場の事情も当然考慮されている訳ですが。)
ちなみに1934年に「嘆きの歌」の初稿第1部の初演が行われたのがまさにブルノであり、しかもそれはチェコ語で行われたこと、更にその初演の翌年のウィーンでの放送のための「全曲演奏」が今回同様の初期稿第1部+改訂稿という形態で行われたことも指摘しておくに値することかも知れません。勿論、今回の稿態の選択にあたっては、とりわけこの極東の地での演奏の伝統がほとんどない作品を取り上げることに伴う様々な技術的な困難をクリアするといった側面が第一義的であったかも知れませんが、理由はどうであれ、結果的にそうしたこの作品の持つ来歴に今回の公演が関連づけられることは興味深く、既に述べたように、実際の演奏において、ヤナーチェクにしてもマーラーにしても、その自在な拍節感が、エッジの効いたスリリングでアクロバティックな名人芸の如きものとしてではなく、ごく自然な間合いと抑揚をもってリアライズされたことは決して偶然ではないと思われます。とはいうものの、私はヤナーチェクの作品については、その演奏について語ることができる程には知識も経験もないため、シンフォニエッタの演奏に関してはその資格をお持ちの方々に委ねることとして、以下では専ら「嘆きの歌」の演奏に限定して述べさせて頂きます。
* * *
上演に会場で接して特に強く感じたのは、オーケストラは勿論なのですが、マーラーの他の声楽を伴う作品にも増して、「嘆きの歌」は合唱、独唱の声楽パートが重要であるということで、独唱、合唱のいずれも素晴らしく、感動的な歌唱であったと思います。特に合唱の効果は素晴らしく、合唱が歌い始めた瞬間に忽ちのうちに緊張感が高まって聴き手を物語の世界に引きずり込む場面に事欠かず、一再ならず感極まるものがあり、その印象は、名手を地頭とする能の地謡を思わせるものがあったように感じます。独唱も皆さん好調で、集中力に富んだ雄弁な歌唱であったと思いますが、特に個別に印象深かったところとなると、どうしても作品の核心の部分を担うアルトの深い感情に満ちた声がまず印象に残ります。特に「歌う骨」の声を代理する、変拍子で歌われる箇所には鬼気迫るものさえ感じました。ソプラノは何といっても特に第3部の最後のクライマックスの殺された弟の告発の語りの部分、マーラーにおいて「嘆き」の形象そのものであるメリスマの節回しが深く印象に残っています。一方でいわば物語の地の語りの役割を果たすことの多いテノールは、能楽でのワキの位置づけに相当すると感じられたのですが、まさにワキの名手の謡が場の雰囲気を見事に設定するのを目の当たりにするような印象を受けました。バリトンは第1部だけの登場で、これまた能楽ではワキツレのような役割を担いますが、テノールとの重唱も素晴らしく第1部の濃密な雰囲気を醸成していたと感じました。
能楽を引き合いに出すことは聊か突飛なものに思われるかも知れませんが、「嘆きの歌」は内容的にも、古作の能に見られるような、素朴ではあるけれど激しくて深い悲しみに貫かれた作品に内容・雰囲気ともども通じるものがあり、その上演は娯楽や教養としてのコンサートのレパートリーであるよりも、寧ろ祭祀における追悼や鎮魂のための奉納に近いものがあると私には感じられます。西洋の伝統に則せば、寧ろギリシア悲劇を先に思い浮かべるべきなのでしょうが(実際、後で参照するナターリエ・バウアー=レヒナーの回想における「嘆きの歌」の初演に関する節ではギリシア悲劇への言及がなされます)、私の乏しい経験の中で近い印象のものを探した時に真っ先に思い浮かぶのは外ならぬ能楽なのです。更に言えば、「嘆きの歌」の歌唱パートの配分は通常のより演劇的な作品(例えば受難曲やオラトリオを思い浮かべて頂ければと思います)で良くあるような、各独唱者に原則として固定的に登場人物を割り当て、合唱が集団の声を代弁するように劇の進行を注釈したり、場面を補足説明したりするといった形態からはかなり外れており、こちらも能楽において、ワキの謡やシテの謡を地謡が途中から引き継いだり、シテが主人公の役割を逸脱して、第三者的な描写をしたかと思えば、ひととき他の登場人物になりかわるといったことが起きるのに近い印象が私にはあります。「嘆き」のルフランもまた、合唱が場面を注釈するように歌うだけではなく、独唱や重唱が担うこともあれば、独唱から合唱へと受け渡されることもあったりしますし、常に固定的な旋律で歌われるわけでもなくて融通無碍なところがあるのは寄稿文でも指摘したところですが、それだけに独唱と合唱が一体となった今回の上演は、作品のそうした特質に適い、その効果を遺憾なく発揮したものと感じられました。
この曲は、特に改訂稿の部分は実演で目覚ましい効果をもたらすべく、巧みにデザインされた部分もあるとはいえ、全般としては20歳になるかならないかのマーラーの、ナイーブと言っても良いようなストレートな感情に満たされていて(質的に近いのは、やはり「さすらう若者の歌」と第1交響曲)、そのまどろみの中で夢見るような箇所(実際それは「さすらう若者の歌」の終曲の中間部、第1交響曲のあの「森の葬式」のカノンに挟まれた中間部で聴かれるものと同じです)と、身を切るような強烈な感情に満たされた悲劇的な箇所との強烈なコントラストは、聴き手の心を掻き乱し心の底から聴き手を揺さぶる、鬼気迫るような側面がありますが、そうした点についてこの公演での演奏は申し分ないどころか、あまり数の多いとはいえない他の演奏に勝る、この作品の本質を闡明する「真正な」という形容が相応しい質を湛えていたと感じられました。
* * *
「嘆きの歌」の上演を巡っては、ナターリエ・バウアー=レヒナーの回想録の「音楽シーズン 1900年ー1901年」の章の「≪嘆きの歌≫ 1901年2月17日の演奏」と題された節があり、そこでは上演に纏わる紆余曲折が記録されています(高野茂訳・音楽之友社刊の邦訳『グスタフ・マーラーの思い出』ではpp.406~8)。それを読むと、作品に対する献身という点で今回の上演が如何に恵まれた理想的なものであったかが却って確認できるわけですが、作品そのものについてのバウアー=レヒナーの印象は書き留められても、マーラー自身の作品に対する思いというのは直接には記録されていないようです。一方でマーラーはその早すぎる晩年に(だが、まさに晩年と呼ぶに相応しい状況下にあって)、ニューヨークからのワルター宛の書簡(1996年版書簡集では429番、1909年12月18日ないし19日に書かれたと推測される日付のない書簡、以下に引用させて頂く、須永恒雄訳・法政大学出版局刊の邦訳『マーラー書簡集』ではpp.389~392)で、自分の第1交響曲を演奏したときに感じたことを以下のように記しています。
「(…)おとといはここで私の≪第一≫をやりました。みたところ、さしたる反応なし、それにひきかえ私はこの若書きに心から満足しました。こうした作品はどれも、指揮するといつでも、妙な気分になる。燃えるような痛切な感情を結晶化している。すなわち、こんな響きと形姿を鏡像として投げかけるとは、これはいったいなんという世界なのか。葬送行進曲とそれにつづいて勃発する嵐のようなものが、私には、あたかも造物主への嘆願のように立ち現れるのです。そして私が新作を作るたびごとに(少なくともある時期までは)この嘆願の叫びが毎回湧き起こるのです――「汝は彼らの父に非ず、汝は彼らの暴君なり!」――(…)」
勿論これはあくまでも第一交響曲についての言及であって、「嘆きの歌」についてのものではありません。ではありますが、同時により広く自分の若書きの作品について述べたものでもあって、私には、それに先立って作曲され、だが上演の方は遥かに遅れて、そのキャリアの絶頂にあってようやく実現に漕ぎ着けた「嘆きの歌」についても、マーラーは同じようなことを感じたのでは、それが故にマーラーは「嘆きの歌」を「作品1」としたのでは、というようなことを、今回の演奏に接することで思わずにはいられませんでした。要するにそれは今回の上演が、「マーラーは、これを音にしたかったのだ」というかけがえのない「何か」が伝わって来る演奏であったということなのだと思います。それはあまりに強烈で、特にその頂点では感情の強烈な波が次々と押し寄せてくるので、少なくとも私に関しては、聴き手としてそれを充分に受け止められたかどうかについては、甚だ心許無いのですが。
そしてそれは単に演奏会場で演奏された作品を、その場で聴取するという条件では尽くせない、ライブ・パフォーマンスの可能性を明らかにするような経験であったと確かに言えると思います。かつてジャパン・グスタフマーラー・オーケストラと名乗っていたオーケストラは現在はその名称に「祝祭」という語を冠していますが、この語はまさに今回のような公演にこそ相応しいと感じられます。このような静謐で悲しみに満たされた、悲劇的で陰惨でさえある作品が祝祭とは、という反応は祝祭という言葉の意味を取り違えているのであって、それならば古代ギリシアの悲劇の上演はどうであったか、否、地球の反対側のことを持ち出さずとも、我々自身の伝統の中にあって、やはり静謐でありながら強い悲劇的な感情に満たされた数多くの作品を持つ能楽の上演はどうなのかに思いを致せば、それこそが「ライブ」の可能性そのものとまでは言わないまでも、その可能性の中心にあるものだということが得心されるのでは、と思います。マーラーの作品であれば、第6交響曲や第9交響曲、「大地の歌」や第10交響曲、更には連作歌曲集といったものも、その上演は単なる娯楽・教養のための消費の場ではなく、まさに「祝祭」の場で上演されるべきものではないかと考えます。
そうした、まさに「ライブ」ならではの経験をさせて頂いたことに対して、演奏者全てに重ねて御礼申し上げたく思います。そしてさまざまな制約から、もう一度というのは大きな困難を伴うことは重々承知しているものの、今回のような機会が再度繰り返して実現し、奏者が十全と感じられる演奏が行われたら、ということを思わずにはいられません。少なくとも今回の上演がそうした「伝統」を形作る、後世に向けての一歩であればということを願わずにはいられません。
* * *