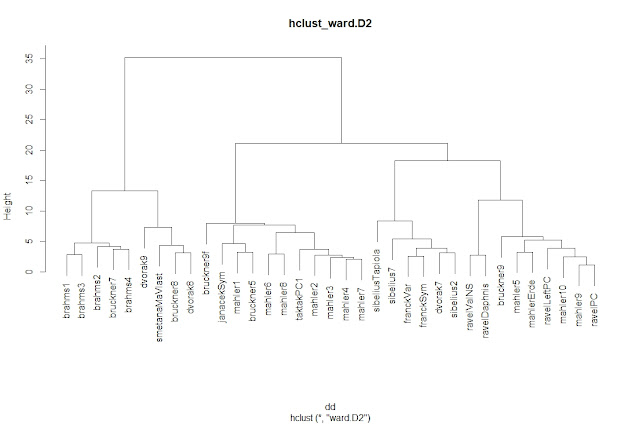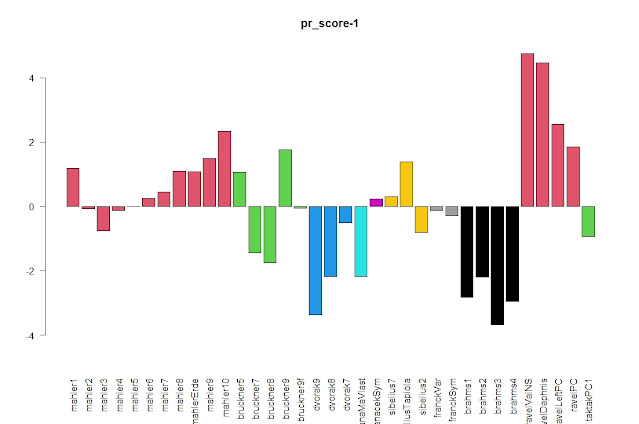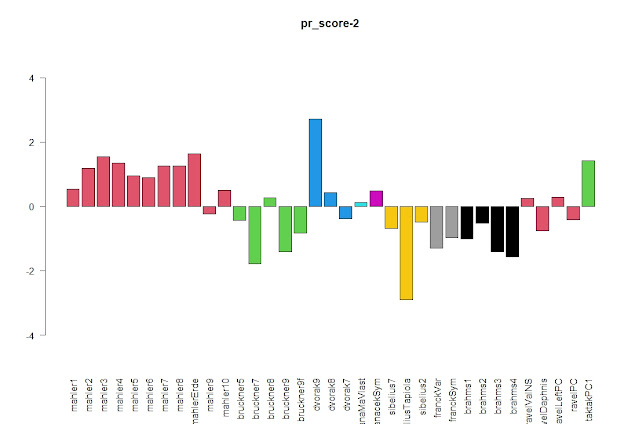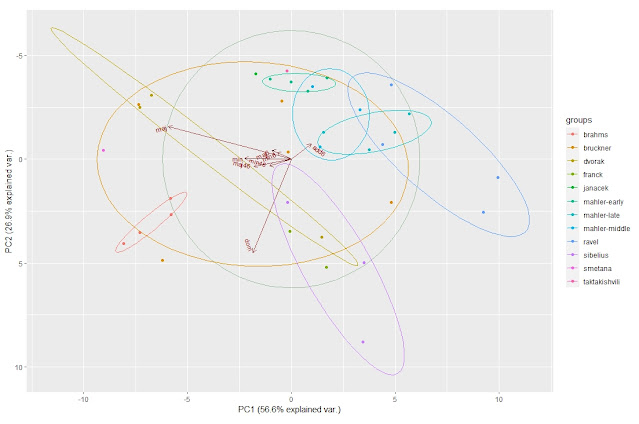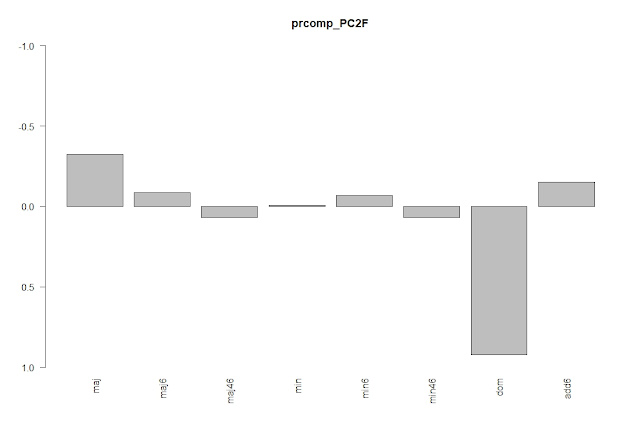以前、通常ならそこにマーラーの名前を見出すことを人が期待することがなさそうな2つの重要な著作、即ちジャンケレヴィッチ『死』とドゥルーズ=ガタリ『千のプラトー』の中に、マーラーの名前が見出され、更にそのいずれもが『大地の歌』への参照を持つことに気づき、備忘として書き留めたことがある。ここで取り上げるジャンケレヴィッチの『死』の方は、高校生の時から知っていたこともあって以前より手元にはあって通読したこともあり、実は『大地の歌』への言及があることも当然認識はしていたのだが、これも別の雑記めいた文章に書き留めたことがあるけれど、その終わり近くに結論めいた形で語られる事実性に依拠するような発想に対して、最初こそ期待できる拠点として検討をしたものの、検討を経るに従って次第に反撥を覚えるようになったという経緯を持つ。更に言えばまずその文体に耐え難さを感じてしまうこともあって、それ自体を主題として論じうるような読解ができず、上述の備忘を記すのが精一杯なのが正直なところであるし、辛うじて読み取れた範囲でも、その見解については直ちに幾つもの疑問が浮かんでしまうような対象ではあるとはいえ、マーラーについて流布する言説の多くが前提としている或る点に対する留保を感じているような場合には、その論点について考える上で貴重な参照点となりうるため、上記指摘に留まらず、もう少し詳細な検討をしたいと考えてきた。
マーラーの後期作品を「老い」という観点から理解するというここでの企図の着眼点は、マーラーの長くはないけれどそれでももう1世紀を超える受容史の中にあって、マーラーの後期作品が常に「死」との関りにおいて論じられてきたのに対し、「死」ではなく「老い」との関りにおいて論じるのがより適切であるという仮説に集約される。従って従来のマーラーに関する言説においては周縁的な位置づけを持ち、だが『大地の歌』への言及を含み、かつ「死」について扱った著作であるジャンケレヴィッチの『死』は恰好の出発点といえるのではなかろうか。実際、ジャンケレヴィッチの『死』は死そのものと同様、その手前と向こう側についても延々と語っており、その中で勿論「老い」についても「死の手前」の中の一つとして論じている(ジャンケレヴィッチ『死』, 仲澤紀雄訳, みすず書房, 1978, 第1部 死のこちら側の死, 第4章 老化)。
だが結論から言えば、あくまでもそこでは「死」が主題であることを思えば無い物ねだりとは言い乍ら、やはり「老い」そのものについて論じているとは言い難く、勿論こうした次元での「老い」は直接には「現象から身を退く」ことをその定義とする「後期様式」とは無関係であるということになろうし、こうした次元の「老い」と切り離してそれらを論じることは、こちらはこちらでもともとのゲーテの言葉を軽んじていることになりかねない。従ってそれは自ずと、ジャンケレヴィッチの「死」についての思索に基づき、それを踏まえ、継承・展開するかたちでマーラーと「老い」について考えるということにはなり得ず、ジャンケレヴィッチの言明に対する異議申し立てを含まざるを得ないから、寧ろそれを反面教師として、マーラーと「老い」の関係についての視座を獲得することを目的としたものにならざるを得ない。ここで企図しうるおとは、あくまでもジャンケレヴィッチに対する批判ではなく、ジャンケレヴィッチの『死』における「老化」に関する叙述を細かく検討することを通じて、マーラーの後期作品、アドルノがジンメルを参照しつつ、ゲーテの箴言にある「現象から身を退く」という言葉によって定義づける作品(その中には、『死』で言及される『大地の歌』も含まれるわけだが)について適切な視座を得る手がかりとすることであろう。
実際後述の通り、ジャンケレヴィッチの『死』の中には「老い」についての章さえ存在するのだが、「別れ」というテーマに関する部分での『大地の歌』への参照とは一見して無関係であるように見え、その限りでは寧ろこれまでの「死」と結び付けて捉える発想の一例として扱うことさえできるかも知れない。「別れ」というテーマに関する部分でのみ『大地の歌』が参照されていることは決して偶然などではなく、「老い」ではなく「死」に関連づけて捉えるという発想との必然的な連関の中で捉えられうるに違いのであれば、マーラーの後期作品が常に「死」との関りにおいてのみ論じられ、「別れ」のモチーフも専ら「死」に関連づけられてきたことに対する批判を、ジャンケレヴィッチの著作の批判的読解を通して試みることが可能であろう。
そこでここでのアプロ―チとして、一旦『大地の歌』への言及がある箇所から離れ、まず「老い」についてのジャンケレヴィッチの扱い方、特に「老化」をこの著作全体の主題である「死」にどう関係づけるかの具体的様相について、些か些事拘泥的と受け止められるかも知れないような祖述的な(だが同時に批判的な)読解を試みる。多分に主観的に私の場合にはそうせざるを得ないという面を否定する気はないが、彼のトレードマークであり、人によってはそれに魅了されることもあるらしく、「交響曲」に喩えられることすらあるらしい、その華麗なレトリックと重厚な論述のスタイルについては、敢えてそれに逆らった読解を行って、その修辞に埋もれがちな「老い」の扱い方を最大限批判的に整理し、その確認結果を踏まえて、『大地の歌』への言及の部分の理解を試みるというやり方を取ることにする。
* * *
「老化の中に死すべき運命の徴候と死そのものの前駆症を読み取ろうという誘惑に人は駆られる。」(ジャンケレヴィッチ, 『死』, 仲澤紀夫訳, みすず書房, 1978, p.202)
とジャンケレヴィッチは「老化」の章を始める。この「老化」の章は彼の「死」についての浩瀚な著作の中で、第1部 死のこちら側の死 の末尾に当たる第4章に位置している。そして直ちに「老化は、一種の稀薄にされた死、引き延され、間隙の次元にまで拡大された瞬間ではなかろうか。」(同)と言い替えて見せる。例によってジャンケレヴィッチのこの問いは多分に修辞的なものであり、従って直ちに矛盾なるものが指摘され、結局は否定されることになるのだが、そこで指摘される矛盾とは、半分はレトリカルで「ためにする」もの、つまり逆説を提示してみせようとする身振りそのものが生み出したものに過ぎないように見える。従って当然、ジャンケレヴィッチ自身はそれを逆説と言い、矛盾と言うのを止めようとはしないのだが、実際にはそれは矛盾などではなく、生の時間の把握におけるミクロとマクロのレベル、より正確には論理のオーダーの差に拠るものと考える方が事象に即した捉え方なのではなかろうかという疑問が直ちに湧いてくる。
「(…)各瞬間ごとにわれわれを実現するものは、各瞬間ごとにわれわれをすこし死に近づける。それは衰頽が人生の第一の段階に続く第二段階として生長に続くからではない。可能性が現存と化することが、すでにそれ自体において、一つの衰頽というべき到来なのだ。」(同)
従ってそのレトリックは措いて結論だけとれば、そして更にここでは「老化」でなく「死」こそが主題なのであって、その限りで「老化」の側について過大な要求することが無い物ねだりであるという点を一旦措いてしまえば、「老化」と「死」とが区別され、異なったものとして捉えられるという点自体に問題があるわけではない。
とはいえオーダーの問題は取るに足らないというわけではなく、既に述べたとおり、「老化」が(「死」がどうであるかについての吟味は一先ず措いて)セカンドオーダーの、複合的・雑種的な側面をもった事象である点を踏まえるのは重要で、ジャンケレヴィッチの記述を文字通りに受け取るならば、
「衰えの眼には見えない前駆症、ごく遠い先の老衰に前駆する予兆は、原則として、ごく初期の幼年時代においてさえ読み取れるものであろう。」(ジャンケレヴィッチ, 『死』, 邦訳, p.203)
というコメントは、一旦は区別した筈のオーダーの違いを自ら無視してしまっていることになっていて読み手の困惑を誘う。ジャンケレヴィッチの記述を文字通りに受け取るならば、例えばホワイトヘッド的なプロセス時間論の文脈での以下の指摘に対応するような水準での検討が必要となる筈ではないか?レトリックのレベルとは別に、ジャンケレヴィッチの議論はしばしば形而上学的な水準の議論と、具体的な生物学的・生理学的水準の議論との間を余りに融通無碍に行き来する感じを否めない。
「(…)われわれは実体・対・属性という永遠的客体に関わる論理を事象の論理と混同し、ここにおいて対象の生成を考えてはならない。常識が陥りやすいかかる考想は、確定的な部分事象の連なりの中で生成を考えることになるから、一事象の生成の時間をとらえることはできない。事象連鎖を通じての生成は、いわば事象の生成にもとづく生成であり、これについての問は論理学的に第二次(セカンドオーダー)の問いなのである。」(遠藤弘, 「時の逆流について(『フィロソフィア』72 所収)」,早稲田大学哲学会, 1984 )
それは「老化」に関する以下の説明からも読み取れる。
「老化した組織が損失を償うのがしだいしだいに難しくなり、損傷を補うのがますます遅くなるように、同様に、(…)」(ジャンケレヴィッチ, 『死』, 邦訳, p.204)
そもそもここでは転倒が起きていて、にも関わらずその転倒した状態で論理を組み立てようとするからこのようになるのであって、本来ない問題を作って、そこにアポリアがあり、パラドクスがあるかの如き議論をしようとしているように感じられてしまうのではないか。
実際には「老化」は、例えばシステム論な立場からは、以下に見るように「生物がもつロバストネスの変移と崩壊」と定義されるのである。
「(…)以上のように、老化という現象には、「階層構造」と「時間」のファクターが組み合わさり、時間軸方向には決定論的にふるまうが、ある時間の断面では確率論的である、という複雑な性質があります。このような複雑な現象を示すシステムとして生物をみた場合に、老化の本質はいったいどのようなものと考えられるのでしょうか。(…)システムの特徴の一つに、「ロバストネス」(頑健性)」という工学用語で表されるものがあります。生物学的な用語でいえば「ホメオスタシス(恒常性)」となるでしょう。(…)システム全体に負荷がかかった場合でも、それを元の状態に戻そうとする能力、それが「ロバストネス」なのです。(…)こうした議論をとおして北野所長とたどり着いた考えは、「老化」は、ロバストネスが変移して、最終的に崩壊する」過程であるというものでした。つまり老化の定義は、「生物がもつロバストネスの変移と崩壊」だと。単なる崩壊ではなく、「変移と崩壊」というところに注目してください。歳を取っても人の体はロバストなのです。(…)ロバストであることに変わりはありませんが、定常の位置が推移していきます。だんだんずれていって、最後に全体としてシステムのロバストネスを保つことができなくなるとついにシステムが崩壊する、つまり「死」に至る、ということになります。」(今井眞一郎『開かれれたパンドラの箱 老化・寿命研究の最前線』, 朝日新聞出版, 2021, pp.229-30)
後に見るように、ラプソディックなジャンケレヴィッチの言明を辿っていくと、実際には彼もこれに近い考え方をしているのではと思わせる箇所にも行き当たるのだが、それを踏まえればここで「…のように」の部分で持ち出された事柄の方が定義の本体なのであって、その点の履き違えを元にレトリックを弄しているだけという感覚を否み難く持つことになる。(勿論、ジャンケレヴィッチに与する人は、それは立場の違いに基づくもので、言いがかりの類であるとして退けるのであろうが。)
だが恐らくはシステム論的な理解とは別の了解に基づいているらしいジャンケレヴィッチはこのようにコメントする。
「生物学上の疲労と生命の躍動の衰頽だけでは、これを説明するのにかならずしも十分ではない。」(ジャンケレヴィッチ, 『死』, 邦訳, p.206)
「かならずしも十分ではない」のは文字通りにはその通りであり、別に間違っているわけではない。しかしことこの文脈に即した限りでは、それはそもそも倦怠の経験と「老い」をジャンケレヴィッチが不適切な仕方で結びつけたからに過ぎない。更に
「生物学上の若返りの秘密が発見されたとしても、わたしはなお老化することだろう。諸器官の老化が抑制されあるいは遅らされても、年月と記憶の重さはわれわれをいっそう老化することだろう。」(同)
というのはいただけない。ここでは永遠的客体と事象のオーダーの差ではなくても、「疲労」とか「倦怠」の分析が適用可能な時間性のレベルと、「老い」を論じることが適切な時間性のレベルの不当な混同がまずある。確かに、個々の器官の水準と、全体としての個体の水準のレベルの違うというのはあって、疲労が主として前者の水準で論じるのが適切なのはその通りだろう。だがだからといって個体の老化が諸器官の老化と独立のものであろうはずがない。一体ジャンケレヴィッチは「われわれ」がどんな基盤の上に立っていると思っているのかを問いたくなってしまう。レベルが違えばそこには断絶があって無関係であるという論理の独り歩きが自ら問題を正しく捉える途を閉ざしてしまうのだ。(もう一つ言えば、この言及は、主観的で一人称的な体験を含むはずの「疲労」の経験を、客観的、科学的な水準の話にすり替えているのでなければ、いつの間にか横滑りしている点でもいただけない。これがジャンケレヴィッチのオリジナリティであるレトリックに由来するものだと言い募るであれば、そのオリジナリティは議論をまともに行えなくする原因であるとして、その価値に留保を付けざるを得なくなるのではなかろうか?)
結局のところジャンケレヴィッチは「死」のみならず「老化」についても形而上学的に取り扱おうとする。それは以下のテーゼにおいて明瞭となる。
「われわれを老化させるのは、純粋状態の”時”だからだ。」(同)
私は「時」は常に具体的な相を持つものであり、純粋状態というのは抽象だという立場なので、そもそもこのテーゼとは相容れないが、ジャンケレヴィッチがそのような手つきで「老化」に見ようとしているものを可能な限り救い出すように努めてみよう。では「純粋な時」の内実は何か?
「純粋の時、つまり漸進的な感覚の荒廃、あらゆる面での新鮮さの枯渇、あらゆる躍動、情熱、確信の鈍化、純潔さの消耗だ。」(同)
ということで、一般的ではあるけれど、寧ろ極めて具体的な意識の状態が列挙されている。そしてそれを是認するように
「なるほど、意識の経験は、一つの恒常的な経験だ。」(同)
だがその続きは「たそがれ」と「秋」とが「憂愁にたえず素材を供給更新する。」となって「恒常性」というのは(意識の存続の期間をその中に含んでしまうような長期に亙る)絶えざる反復であるとされる。そしてその果てには(さっきはそれで尽くされることはないと言ったばかりなのに)再び「疲労」が参照される。
「疲労の曲線には上昇下降の間に最高潮があるが、器官の老衰の図式あるいは縮図もそのようなものではないだろうか。」(同)
だが(またしても、だが結論だけ見れば正当に思われることに)結局、この繰り返し・反復への依拠もまた放棄される。結局「老年」は一回切りの経験とされるのである。これが「われわれを老化させるのは、純粋状態の”時”だからだ。」というテーゼとどういうふうに接続されるのかが気になるところではあるが、それは一旦措いて更に彼の論理を追ってみよう。
「自然における衰頽は、悲しいかな、まことに真剣で、まったく詩情に欠けている。この衰頽は、ただ単に逆行不可能なだけではなく、その上決定的なものであり、とくに一回限りのものだ。」(同書, p.207)
要するに「疲労からは回復するが、老いからの回復はない」と一言言ってしまえば済む話なのだ。だがここにもスケールの、レベルの混同がある。「漸進的な感覚の荒廃、あらゆる面での新鮮さの枯渇、あらゆる躍動、情熱、確信の鈍化」という意識の経験の水準では、一時的にそれが中断し、或いは恢復することすらあり得るだろう。老いが一回性で、不可逆であるとするならば、そうした認識は別のスケールで行われているというべきなのだ。従ってジャンケレヴィッチの議論は、その指摘のある部分の妥当性にも関わらず、論理的には破綻していると言わざるを得ないだろう。
繰り返しになるが、ジャンケレヴィッチの「老年」に関する主張そのものは、実際にはシステム論的な定義に対立するものではないし、それは器官レベルとは異なるレベルで把握されるものであるというのも間違いではないし、一回切りというのも間違っているわけではない。だがそれは器官レベルと無関係ではなく、寧ろそれに基づくものでなくてはならないし、また「意識の経験」なるものをそれと独立のものとして特別扱いするのはおかしい。「意識の経験」は実際には、それがダマシオの言う中核意識ー中核自己、現象学的な第i一次把持に関わるレベルであれば、器官レベルと同じ水準で捉えられるようなものであり、寧ろ「老化」はそれを超えたダマシオの延長意識ー自伝的自己、現象学的には想起と予期の水準である第二次把持、更にはスティグレール(およびユク・ホイ)の言う第三次把持が関わるような、技術的・文化的・社会的に規定される水準に関わるのである。そして「一回性」というのは、このレベルで言いうるものであって、そのレベルが、生物学的システム論的には、器官のレベルとは異なるレベルでの「生物がもつロバストネスの変移と崩壊」に対応する筈なのである。私の立場からは、実際には「生物がもつロバストネスの変移と崩壊」という捉え方の方が、一回性という意識の経験、意識にとっての見えを生じさせる根拠であって、「純粋な時」など不要だし「意識の経験」を根拠におくのは、(勿論、それを「意識」することができるのは、少なくとも延長意識を備えた生物に限られるという点はあるにせよ、あくまでも「意識の経験」は結果であって)遠近法的倒錯の産物に過ぎない。
一方で「老化」の不可逆性について(実は厳密に言えば、その不可逆性は確率的なものであって、一時的な回復だって一定の確率で起こりうる筈なのだが)の具体的な例示については問題はない。だが「疲労」と「老化」の違いを述べながら「疲労というちいさな老年」「老年という大きな疲労」というようなレトリックを振り回すのに何の益があるのかは判然としない。「老化は時間性の病」という定義も直ちに「正常であると同時に病的なものだ」というほとんど空虚な言明に引き継がれ、「死が健康な人びとの病気であるのと同じ意味で」という比較もそうした比較に何の意味があるのか杳として知れないまま第1節は閉じられる。
* * *
そして第2節が始まると「老化はわれわれにすこしずつ死をあかすというのだろうか。」と述べられているのを見て、多くの人は絶句するのではなかろうか。一体第1節のゆきつもどりつの議論は何だったのだろう?ただしこの著作は、老化についてではなく、「死」についてのものであることを思えば、老化はそれ自体が議論の対象というよりも、それを「死」に引き寄せて見たり、対比させてみたりといった気儘な操作の対象に過ぎないのかも知れないが。かくしてこの冒頭から窺えるように、第2節はほとんど「老化」に関して言えば無意味な節ということになってしまう。唯一末尾近くの
「時の展開は、存在と事物に毀損作用を働くのだから。時は分解の次元とも言えよう。」(同書, p.212)
という箇所のみが意味ある発言であるように見える。但しこれはエントロピーの増大が時間の向きであるという言明に過ぎないのだが。だがジャンケレヴィッチはこれを彼が「おおざっぱな隠喩」と呼ぶ「骸骨が老人の痩せた肉の下にしだいに見えるようになる」という表象に結びつけてしまう。そんな隠喩に勝手に結びつけるのがいけないのであって、そんな隠喩よりも「時は分解の次元」の方がよほど「老い」に関しては実質的な言明であるのだから、ここでも論理の向きが本来とは逆になっているのだ。
だがそんなことはお構いなく、ジャンケレヴィッチはくだんの隠喩に拘って、それを延々引き摺り回した挙句、末尾の
「老化がしだいしだいに老衰する組織の中に死をますます明白なものとはしないだろう。」(同)
と、その隠喩の不適切さを論じて節を結ぶ。自分から隠喩を持ち出しておいてそれを不適切だと断じるのであれば、初めからそんな隠喩を引き摺り回す必要などないのだ。老化は、生物という物理システムの定常状態の変移と崩壊を指すのだから、死はその変移の帰着点に過ぎず、単に彼が引き摺り回す言明の言い回しが事象に即した時に不正確なだけであろう。
* * *
ところが、第3節の冒頭でもまた、その不正確な言い回しを引っ張り出して批判をして見せる。そこから彼の言葉によれば「弁証法的」で「非一義的」ということになるらしい、正しい定義にようやく取り掛かる。まずは「老化は死にわれわれを近づける。」これは定常状態の変移の向きが最後に崩壊に至るものであることの言い換えに過ぎない。
「組織と血管の硬化、骨の漸進的脆弱化、心臓の疲労、そして老眼は(…)無気力の侵入の前駆兆候だ。」(同書, p.213)
違う。それらは前駆兆候ではなくて、無気力をもたらす原因だろう。
「生命の機能が徐行し始める。」(同)
これは定常状態の変化の向きを述べているのだとすれば彼のお好みであるらしい「隠喩」としては妥当だろう。
「細胞が老化し、動脈が老化して、毒素や毒性が長い間に毎日すこしずつ体液の科学的構成をそこねる。」(同)
一体、ここでいう毒素・毒性というのは具体的には何なのか?実は「老化」の機序は現時点でも明らかになったとは言い難く、解明が困難な問題であり続けている。それを前提にすれば、一見おおまかな把握としては妥当そうに見えるが、この「毒素」の説明が妥当だとするならばフロギストンによる燃焼の説明だって妥当だということになる。否、実際にはそんな毒素などなく、毒素が増えて行った結果死に至るという事実は確認されていないようだし(勿論、間接的に死に至る症状を引き起こす原因となりうる変化はあるし、その変化を引き起こす化学物質は幾つも知られているが、それは死の直接的な原因ではない、一義的に老化を引き起こす遺伝子というのは存在せず、個別には関与する遺伝子が突き止められているものもある様々な促進作用と阻害作用の合力の結果なのだ)、今後そのような毒素が発見される可能性も限りなく低そうだから、寧ろこの説明は端的に出鱈目だと言うべきか、百歩譲っても現時点では不要な程にまで不正確だと言うべきなのだろう。
この辺りのジャンケレヴィッチの言い回しのことごとくが、そうした歪みを持った文学的修辞に過ぎず、要するに、ジャンケレヴィッチの関心事は、老化自体ではなく、老化に纏わるレトリックの方に専ら存するのではないかという疑いが生じてくるのは避け難い。
「あたかも死の向地性とでもいうものがすでに墓へと引き寄せるかのように、あたかも自分自身の重みでもう冥界へ、大地の奥深くへと傾いてゆくように、身体自身が曲がってくる。」(同)
老化で腰が曲がり、背骨が曲がるのは、死の向地性のような文学的表現とは関係がない。それなら直立歩行に至る前のホモ属は、より死に近かったとでも言うのか?このような、読んでいて当惑を感じる他ないような記述を延々読まされると、思わずソーカルとブリクモンによる『知の欺瞞』において、判読可能な文章は一握りで、あるものは陳腐で、あるものは間違いと断定されてしまっているドゥルーズの無限小解析についての長大な記述(ソーカル、ブリクモン『知の欺瞞』, 田崎晴明, 大野克嗣, 堀茂樹訳, 岩波書店, 2000, 岩波現代文庫版, 2012, p.239~247参照)を思い起こし、それに付き合わされるのと同様に時間の無駄でしかないように感じられてしまう。勿論こちらは科学の濫用ではないけれども、その華麗な修辞に埋もれた論理を追うことがしばしば困難である点では共通性があるように感じられる。文学的な比喩表現を不要視する訳でも、否定する訳でもなく、それが適切な場面もあるだろうが、「死」との関りにおいて「老化」を把握するのに文学的な表現を幾ら尽くしても、「老化」が主観的な経験のみで尽くせる訳ではなく、客観的な事実を無視することができないことは勿論、主観的な経験にしても現象学的な水準での記述や分析の対象であって、純粋に論理的な操作や形而上学的な直観のみで扱う対象ではない以上、それによって何かが明らかになることはあるまい。言葉の上でだけ、見せかけの対立を作り出して逆説を弄び、概念を厳密に操作する替わりに横滑りさせることを繰り返したところで、それは「老い」そのものとも、「老いの経験」とも無関係な戯れに過ぎず、そこから何かが得られることはない。「死」が彼のお気に入りのテーマであり、更には彼の修辞にとって恰好の題材であるのとは対照的に、「老い」は散文的で現実的に過ぎて、「何だかわからないもの」や「ほとんど無」の、或いは「筆舌に尽くしがたいもの」についての哲学者であるジャンケレヴィッチ好みの高尚な形而上学的な直観の対象にはふさわしくないのかも知れない。
* * *
そして「老化」についてのジャンケレヴィッチの議論の行き着く先は、章題にも関わらず(だが、案の定と言うべきか)「老化」についての分析ではないようだ。最終節である第4節が、「死刑囚」についての議論で開始されることがそれを端的に物語っている。「死刑囚」は勿論「老い」とは何の関係もない。そして「死刑囚」について論じることは、「老い」固有の問題ではなく、寧ろ端的に「死」について論じることにならざるを得ない。であってみれば、それを「老い」の章の最中で、しかもその末尾の節の冒頭に据えるのであれば、そもそもジャンケレヴィッチは「老い」についてなど議論する気がないのだろうと考えざるを得ない。但しここで、死刑囚が獲得する「二重の視点」「共観的」「回顧的」「第三人称的」な視点が問題であって、それを可能にする意識の構造が「老い」の認識に関わるということに限れば、これは主張として問題ないが、もしそうであるとしても「老化」とは無関係な「死刑囚」をわざわざ持ち出す必要などない筈である。だがその点は一先ずおいて先に進もう。
「老化は、限られた可能性の貯えが徐々に消耗していくことに還元されよう。」(同書, p.220)
この観点を取ることを可能にするものをジャンケレヴィッチは「超意識」(同)と呼ぶが、その定義の「生成の全体を俯瞰する」(同)というのも曖昧さに満ちた言い方で、「生成の全体」なるものが何であるかを考えれば不正確でさえあるだろう。ここでも問題はマクロとミクロのレベルの違いなのだが、「継続する出来事の後を追って地上をはい回る」(同)だけであれば、意識の中断を挟んだ過去の想起と未来の予期を可能とする第二次把持のメカニズムすらいらない。そしてここでいう「生成の全体」の生成は、例えばプロセス哲学的にファーストオーダーである無時間的「生成」でなく、事象の論理のレベルであることは、「生涯」といった言葉が論述に紛れ込んでいることからも明らかだろう。そればかりか(システム論的に定義可能な「老いそのもの」ではなく)「老い」の意識は、自伝的自己の持つ延長意識を俟って初めて可能なのだ。だがジャンケレヴィッチは結局、老年というのは生命の「色調」とやらの「質」の違いということにしてしまう。
「老年は生命力の衰頽の一つの形だが、この衰頽した生命力はそれでも一つの生きている生命力だ。そこで、老人の生命力はその量的な濃厚さ、つまり、存在の質と重さでは成人の生命力と変わらない。ただ、質が、生命の色調の特徴が異なるのだ。」(同書, p.224)
これを隠喩であると言わず、かつ「色調」がどのように定義され、計測されるかが示されることなく、「青春と老年とは、生命の色調の変形であり、質を異にする実存の様態」(p.225)と繰り返されても読み手は困惑させられるばかりである。ここで「質」を持ち出すについてはジャンケレヴィッチの独創というわけではなく、彼が依拠するベルクソンのそれに従ったものであるらしいが、結局のところ言われるのは、実際には「老化そのもの」と「老いの意識」の区別に過ぎず、ボーヴォワールなら、外から見た老いと内側から見た老いと区別するところを以下のような言い回しで述べているに過ぎない。
「老年について語るとき、客観的な系列と生きた系列を混同することは避けねばならない。前者は、たとえば癒着の時間あるいは反応の時間の延長、条件反射の緩慢化のように、数あるいは量で表されるいくつかの原因の尺度上の進展によって特徴づけられ、後者は、生きた経験の質の変化に存する。」(同書, p.225)
確かにある尺度によって測定される生体の生理的な状態と、意識によって経験されるものは異なるが、だからといって両者は無関係ではないだろう。後者は前者の影響を逃れることができない一方で、確かに後者が(つまり或る種の思い込みが)前者に影響する(体調を悪くする)ということも起きうるであろうが、老化というのは、その両方に亘る事象、複合的な出来事と寧ろ言うべきであって、ジャンケレヴィッチの区別への拘りは単なる不毛にしか通じないように感じられる。
「≪変質≫は、意識が”他者”—であって少なくではないーとなる過程だ。」(同)
というのは、他性についての定義を欠いている以上、それ固有の歪みを持った比喩に過ぎない。更に言えば、まさか老いることが文字通りに「他者になる」ことであろう筈はなく、寧ろ意識の中断を挟んだ自己同一性があること、自伝的自己を備えていることが老いの経験にとっては不可欠なのだから、ジャンケレヴィッチの比喩は寧ろ不適切な歪みを持ち込む弊害の方が大きいのではないか?
だがそうしたことに目を瞑って、ジャンケレヴィッチの言わんとすることを捉えようとするならば、結局、彼にとって「老いとは老いの経験のことだ」ということに尽きていて、それを言うために延々と繰り言を述べているに過ぎないように見える。
例えばシェーラーが、「年齢と戸籍とは無関係な一種の≪形而上学的≫老化」(同書, p.226)を信じていたというようなことを傍証として持ち出すが、これは老いの体験というのが、個体により、或いは同一の個体であってもその折々の心的な状態に応じてさまざまであって、前者であれば、これは老年学という社会学の分野においては「老い」の進行は確率的な事象であって、年齢に正確に対応した事象ではなく、その発現と進展には統計的な揺らぎがあるということを酷く曖昧な仕方で述べているに過ぎないと一方では思われるし、更に別の話として、生理的な老いとそれについての意識の経験とは別に、自伝的自己が持つ老いについての認識(だからそれは老いに纏わる様々な身体的・心理的事象の経験とも別のものである)というものがあって、それは年齢を問わないということであるとするならば、こちらはこちらで、これまでジャンケレヴィッチがさんざんそうしてきたように、本来区別されるべき事柄について不当に混同をすることによって可能になったレトリックに過ぎず、言葉の上のことに過ぎない。
そしてそうした自己のレトリックに起因する混乱を脇に置いて
「老年はいつも死の逼迫接近によって測られるわけではない。近接と距離とは空間上の映像であり、社会の概念ではないだろうか。」(同)
といって、それを社会に押し付けるのは不当に思われるし、そのことを
「老年は暦の上の一つの日付にも道路の距離にも還元されないのだ。」(同)
と結論づけるのも筋違いにしか感じられない。勿論、複合的な事象である「老い」には社会的な側面が存在するのは確かなことであり、だからジャンケレヴィッチがそれを「社会的」測定から引き離そうとするのはそもそも無理筋というものだ。確かに「老い」が暦という人間の生理的なリズムとは異なった、天文学的な基準によって定義された尺度と無関係なのもそれ自体は正しいし、更に言えば、そうした暦が社会的なものであるということもまた正しく、その限りでは妥当であるが、だからといって、そのことから「老年」が社会的なものでないということは導かれない。ここの言明の間を結びつける論理については、ジャンケレヴィッチのそれは曖昧なレトリックに凭れ掛かった言葉の上だけの遊びであって、事象に即して言えば出鱈目であり、ナンセンスであり、全く間違っているという他ない。恐らくここで言いたいのは、要するに「老いの経験」は主観的な経験なんだから、外からは測定できないのだという、如何にも亜流ベルクソン的な発想に基づく主張なのだろうが、これだけ贅言を尽くしてなお、それで結局「老い」とは何に基づく経験であって、結局のところこの浩瀚な著作の主題である「死」とどのような関係にあるのかについての議論は、さっぱり深まっていないように思われるのは錯覚なのだろうか?
実際には彼の、およそ適切とは思えない用語法では「超意識」と呼ばれるもの、現象学的には第一次把持に相当するダマシオの言う「中核自己」のレベルを超え、「自伝的自己」による俯瞰を可能にするのは、一方で彼が「共観的」「第三者的」という言い方をしていることから窺えるように、まさにそちらの方が社会的であり、現象学的には第二次把持のみならず、スティグレールやユク・ホイが言う、第三次把持がテクノロジーに基礎づけられているという事実、或いはアンディ・クラークが言うように、今日の人間は生まれながらのサイボーグであって、言語も含めた技術的補綴によって成り立っているという事実に基づいているのだし、そうしたテクノロジーの侵入を措いたとしても、「超意識」はそれ自体の発生において、そもそも社会的に基礎づけられたものなのだから、ジャンケレヴィッチの主張は支離滅裂にしか映らない。それは自分の背中を見ることができず、自己が成立する以前の、自己が如何にして成立したかの機序について「知りえない」とする(スティグレールやユク・ホイ、クラークの名誉のために付け加えれば「かつての」)哲学者の野郎自大が齎した歪みが露呈しているに過ぎないのだ。
だがなおも「老いの意識的経験」に拘るジャンケレヴィッチは「動物は衰頽するが、自分自身の衰頽には立ち会わない。」(同書, p.229)といった主張をしてみたりもするが、これは事実の問題として、動物学の領域では今や人間の側の傲慢さに基づく先入観に侵された不当な断定として問いに付される主張だろう。動物の方はあくまでも話の枕で、人間が「超意識」を持っていて、その「超意識」が老いにとって重要だというのなら、それは別に構わないのだが、だからと言って、今度はその意識について
「老いるという意識は、したがって、厳密に言えば、直接の経験にも推論にも由来するものではない。」(同書, p.230)
などと主張されると、一見当たり前の事を言っているように見えるこの主張の真意を測りかねるということになる。実際にここで言われているのは、老いの徴候とされる、様々な観察・観測の結果は、それが老いの徴候であるという解釈が先行的にあって、観察結果について判断し解釈する主体(老人自身であれ、医師であれ、或いは介護レベルの認定をおこなう行政の担当者であれ)があってのものであるという、ごく常識的なこと以上のものではなさそうにしか見えない。そして一般的にはそうした水準で、推論に基づいて要介護度の認定が行われ、認知症の診断が行われているのである。私はその場に立ち会った当事者の一人だから、その経験に基づいて言えば、勿論、主体に対するインタビューも欠かさず行われていて、主体の証言も記録はされるが、それを文字通りに受け取ることが、主体の内側で起きていることを正しく判断することに繋がらないこともまた、現場では常識レベルのことであって、結局のところ解釈や推論抜きで「主体」についての真実を見出しうるというのは、本質的に関主観的で対話的な存在である筈の主体自身にとっても幻想に過ぎないのだ。にもかかわらずジャンケレヴィッチが以下のように言うとき
「(…)居眠りが繰り返されることや、固有名詞の忘却、視力の減退、階段を昇るさいの困難の増加などを老化の徴候と解釈する主体を無視した推論については、象徴にもとづいて意味を結論するそのような抽象的推論は、それだけではわれわれを説得にするのには十分ではない。」(同)
彼は「われわれ」の中に自分自身以外の誰を含めて想定しているのだろうか?権利上、それが自分が理性的存在者の代表であり、理性的存在者は皆自分のように考えるという哲学者のお目出たい傲慢さでないとしたら、彼の恣意で決定できるような誰かが彼以外に他にいるのだろうか?この言明は、「いや、私にとっては十分に説得的ですよ。」という反論にどう答えようとしているのか?いや、これは哲学であって実証的な科学ではないから、事実水準の話ではなく、権利水準の話をしているというなら、それならそれでつまるところ、この言明によってジャンケレヴィッチは何を表明したいのか?
だがここでは「老い」を取り上げるのが最終目的であって、ジャンケレヴィッチの著作を吟味すること自体が最終目的であるわけではないから、その点について目くじらを立てるのは程々にしよう。
「衰頽は誠実な直接の経験というよりは、むしろ一つの解釈であり、一つの判断なのだ。」(同)
と、この言明自体は全く問題ない。そう、繰り返し述べているように、「老い」というのは複合的で雑種的な事象なので、それを直接測定できる指標が存在するようなものではないから、その限りで解釈や判断の結果であるという主張自体には特に問題はない。そして恐らくその点において「老い」は「死」とはやや性格を異にするのであろう。勿論、生死の判定に纏わる様々な困難は、それらもまた「老い」のように解釈や判断に委ねられる側面を持つことを示唆しているけれども、だからといって「老い」がそうであるのと同様にそうであるとは言い難い。「老い」の厄介さは、そのシステム論的定義を改めて確認し直せばわかることだが、それが非常に複雑なシステムの「定常状態」の変移という非常に巨視的な仕方でしか定義できないという点にあり、なおかつ、その変移について、系自体が崩壊する方向に向けての変化という仕方で定義されるのであって、崩壊そのものの程度(こちらは「老い」でなく「死」への接近の度合いという意味合いを持つだろうが)で測られるものではないことに存する。なおかつその過程は現実の個々の事例について言えば確率的な揺らぎの中にあって、必ずしも単調な変化ではなく、複雑な軌道を持ちつつも、最終的には系自体が崩壊するに至るように方向づけられた過程なのである。
ジャンケレヴィッチも勿論そうした複合を無視しているわけではないから、「老い」を複合的な原因を持つものとして捉える言明と解釈できそうな言明が登場しはする。
「正常な状態では分離されているこのような経験とこのような観点とが互いに干渉し合う時、老いるという意識が生ずる。」(同)
ここで「このような」とは、「客観的観点は生きるべき期間の有限性を認めることができるが、その有限性をただ他人にとってのみ有効な真実とみなしたがる。生きた経験は、自分にとって有効だが、死を受け入れない。」(同)という観点と経験の謂いである。
だがこれもまたごく平凡に、既述の老いの定義に纏わる厄介さについての言明の言い換えの類に過ぎない。生とは散逸系である生物学的なシステムが存続する「定常状態」のことであり、動的不均衡の中で、準安定的な状態というのが維持されているわけだが、ここでいう客観的観点の側は、その安定状態が、軌道を描いて変化しつつ、最後は崩壊する過程の外部からの観測であり、ここでいう生きた経験の方は、そうした系自体の内部からの観測のことを言っているのだから、結局この言明も構造的には何ら新しいことを言っている訳ではなく、「生理的な老いの過程」と「老いの経験」の複合が「老いの意識」を生み出すと言っているのであって、その限りでは構図は問題ないが、だがジャンケレヴィッチの文脈におけるその実質は、またしても疑わしい。外部からの観測と内部からの観測における差異が問題であるとしてなぜそれが「生の有限性」についてでなくてはならないのか?確かに老いの認識は生の有限性の認識でもあろうが、それだけではないし、寧ろ生の有限性という「死」に関わる側面以外の部分こそが「老い」固有のものなのではないのか?だとしたら、そこにはここででっち上げられたような観点と経験の干渉などありはしない。寧ろ単純に両者が相俟って「老いの意識」が生じるというだけで十分ではないか。
実際にはその後しばらくのジャンケレヴィッチの叙述はようやく「まともな」ものになるかに見える。まずはベルクソンを参照し、
「感覚の質の変化が刺激の増大の尺度に度合いも進展度もすこしも反映しない」(同書, p.231)
点を述べる。これは特に問題ないし、
「記憶は大脳におおまかに依存するが、回想は大脳皮質のそれぞれの場所に文字どおり位置づけられているということはなく」(同)
というのも、或るタイプの記憶の想起を支える機構の説明として問題ない。(なぜそれが併置されるのかの論理、或る種の記憶と想起のメカニズムの非局在性が、この際どういう関係があって言及されているのかについては目を瞑ってしまえば。それはベルクソンの元々の言明とも関係なければ、老いとも関係ないから、これは奇妙にしか映らないのだが…)そして、
「人の質的老化が毎日詳細にわたって人生途上の進展をそのま訳出しているというのも真実ではない。詳細にわたってというのは真実ではないが、おおまかに、間接的にというのは真実だ。」(同)
というのも問題ないだろう。老いという定常状態の軌道は(数学的な意味で)単調に崩壊に向かうわけではなく、揺らぎをもって、確率的に動いていて、その軌道というのは粗視的に見た時に浮かび上がってくるものなのだから。
一方で、「老い」の自覚は、そうした連続的な過程の非連続的な感受に基づくものであるというのもまた、それ自体は正しいだろう。それゆえ、ボーヴォワールの『老い』においても印象的な仕方で繰り返し語られるように、「老い」とは或る日突然に自覚されるものでありうるわけだ。
「身体の連続的変貌は時を隔てて、つまり、間歇的、不規則に意識に現われる。老化は漸進的なものだが、老化の意識はそうではない。」(同)
その通り。但し、老化自体が確率的な過程であることと、老いの自覚が突然に生じることは、厳密には区別されるべきだろう。前者によれば、若返りの自覚というのも時として可能ということが帰結し、実際にしばしばそのような経験は生じるであろう。寧ろ逆に、揺らぎを孕みつつ、エントロピーの増大という熱力学的過程に従うかのように巨視的には崩壊に向いた過程であるということが、間歇的・不規則な内部観測における老いの自覚に繋がっているのだから、ここにも避けるべきレベルの混同の嫌疑が生じるような書き方に眉を顰めざるを得ない。とはいえ、言明自体はここについては適切である。
だがもう良いだろう。ジャンケレヴィッチの「老化」の章の結論部分においては、「感得」がキーワードであり、その点について確認することでジャンケレヴィッチの議論の要点を確認することができるだろう。そしてまた、この「感得」こそが、ジャンケレヴィッチにおいて死と老化を関連付けて論じることを可能にするポイントでもあるだろう。
「”真に受けること”にほかならないこの自意識、男も女もはじめて時の消滅に気づく老化の意識をわれわれは≪感得≫と呼んだ。感得は生きた時と鳥瞰した時の最初の出会いだ。」(同書, p.233)
ということは、基本的には内部観測の結果と、外部観測の結果の突合こそが老化だということで、これは数ページ前に述べられていたことの繰り返しに≪感得≫というラベルを付けたということになる。そして≪感得≫についての3つの相というのが再び確認される。ところがここでの言い回しからわかるように≪感得≫はもともと「老化」について導入されたのではなく、まさに本題である「死」について導入されたのだ。それを事も無げに、断りもなく「老化」に適用してしまって構わないのだろうか?
その是非を措けば、そうした挙措はジャンケレヴィッチが「死」と「老化」の関係をどのように捉えているかを問わず語りに告げているということになるのだろう。そして実際、そこでは「老いてゆく人間」が主語の場合でも、「老い」ではなく「死」との関係が論じられてしまう。曰く、
「老いてゆく人間は、感得することによって、予告と自分自身の死の結びつきを把えないならば…」(同書, p.234)
或いは、
「年老いてゆくものが、自分自身の死の日(時計上の時・分、暦上の何日)を文字どおり知るのではなく、死の近いことを強烈に経験するのだ。」(同)
従って
「≪感得≫のこれらの三つの相は、老化の経験においては、もちろん互いに切り離すことができない。」(同)
という言明の当否に依らず、ここでは「老い」そのものではなく、「老い」における「死」が問題になっていて、最早「老化」そのものについての議論は終わっているということに読者は気付かされることになるのだ。この言明以降、この節の末尾まで、ということは「老化」と題された章の末尾まで、ということでもあるのだが、とうとう「老い」という言葉は全く出て来なくなり、ひたすら「死」の≪感得≫について語られるばかりである。だが、その末尾までの言明を見て、一体それが「老化」とどう関わるのか、訝しく思う人がいても不思議はない。そこに書かれているのは、この節の冒頭の「死刑囚」の話がそうであったのと同様に、「老いてゆく人間」にのみ専ら関わることでもなく、「老い」と独立に論じることができることなのである。振り返ってみれば、「老い」についての議論の末尾で客観的な知識なり認識なりと、生きられた経験の相互干渉が「老いの意識」を生み出すとされたのであったが、結局のところそうした知識を一人称的に”真に受けること”が「死」についてと同様「老い」についても重要なのだということがジャンケレヴィッチの謂わんとすることなのかも知れない。
だがもし仮にそうであったとして、「死」とは異なった「老い」の経験自体、「死」に対する「老いてゆく人間」ではなく「老いてゆく人間」が「老い」そのものにどう対するのか、「老い」固有の悲劇性がそこにあるのではないかという疑問についてジャンケレヴィッチが答えてくれることは期待すべきでないだろう。それは自ら引き受けて、自ら答えていくべき問題なのだろう。ボーヴォワールの『老い』は例外的に老いそのものに正面から立ち向かった試みであるが、その中でアンガージュマンの人らしくボーヴォワールが告発するように西洋の文化や社会は「老い」について正面から取り組むことを避けてきたのではないか?「死」についてはあれほど饒舌で、「死」についての著作なら古今を問わず汗牛充棟の状態であるのに対して、「死」そのものでもなく、「死」の前駆でもなく、直面することを強いられる「老い」そのものについて語られることが何と少なく、「老い」の議論がいとも容易に「死」についての議論にすり替えられてしまうことか…そしてそのすり替えの、まさに典型的な例をジャンケレヴィッチのこの著作に見出したような気がする。
* * *
ここからは急ぎ足で、これまでの「老化」についてのジャンケレヴィッチの記述の追跡の結果を踏まえて、改めて『大地の歌』への参照箇所についての検討を行ってみたい。『大地の歌』への参照は、第2部 死の瞬間における死 の第3章 逆行できないもの の掉尾を飾る第9節 訣別。そして短い出会いについて で行われる。ここで直ちに気になる点は、第2部がその看板が示す通り、死の瞬間のみについて語るのだとすれば、逆行できないものというのはそもそもナンセンスということになることである。実際、それは先行する第2章で、ほとんど無 について語る時、既に、厳密な意味合いで瞬間に属さないものが密輸されているところから破綻していて、第3章は更に大胆に、実質的には再び「老い」について語り直しているようなものだ。
そもそも「老い」について語った時、老いこそが一回性で、不可逆であると言っていたのではなかったか?だとすれば、その構成上の位置づけにも関わらず、『大地の歌』への参照は、実際には「死」そのものよりも寧ろ「老い」について語る文脈において行われているとさえ言い得るのではなかろうか?そして実際、第9節 訣別。そして短い出会いについて は冒頭でいきなり
「だが、この償われない喪失が人を慰められないままに残すとしても、老いてゆく人間がまったく補償に欠けているというのではない。」(同書, p.351)
と、老いにおける「補償」について語りだすのを見ると、それは確信に近いものになる。
「別離という数多くのちいさな死が、死という大きな別離の楕円を形作っているからだ。」(同書, p.352)
というレトリックも既視感のあるものだ。果たして老化について語っていた時には「疲労というちいさな老年」「老年という大きな疲労」というようなレトリックを振り回していたのである。しかもここでの「告別」は、火星探査を引き合いに出して語られるのである。この点は決して取るに足らないことではない。アドルノが宇宙飛行士の見る「地球」についてまさに『大地の歌』に関連して述べていたことを思い起こし、火星への植民をビジネスにしようというイーロン・マスクが使い捨てのロケットではなく、帰還して再利用ができるロケットの開発をしていることを思い起こしてみるがいい。ここでのジャンケレヴィッチの主張のポイントは、「死」は一回性のもの、不可逆なもので、死の瞬間の近傍のトポロジーは、彼自身の著作の構成を裏切っていて、死のこちら側と死の向こう側は対称ではなく、(そういう言い方をするならば)「死出の旅」は片道であることが「告別」の持つ意味合いを、一時的な別れとは全く異なるものにするという点に存する筈である。寧ろ、死のこちら側というのは、死の「手前」というのが適切であって、かつそのトポロジーを決めているのが「老化」である筈なのだ。当然だが、「告別」は死の手前で為される。であるからには、一回性の、一度限りのそれは寧ろ「老い」に固有のもの、寧ろ「老い」に帰属させるのが妥当なものではなかろうか。
そして悲劇性についても、ここでは「不在に先行した別離は悲劇性そのもの」(同書, p.353)と言われているが、「老化」に関しては、
「≪悲劇的なもの≫とは、人を突然≪老化した≫状態に置く一連の状況の名だ。」(同書, p.217)
と言われていたことを思い起こすべきだろうか。ジャンケレヴィッチお得意のレトリックを剥がしてしまえば、これはボーヴォワールが『老い』の第2部 世界内存在 で扱う、老いの認識に関わるのであり、老化を突然自覚することに関わる筈である。勿論、老いの自覚は「告別」によってもたらされるとは限らない。というより寧ろ、「老い」の自覚に導かれて人は「告別」をするのではなかろうか。「告別」が人を「老化」させるのではないが、「告別」は老化の自覚なしにはありえない。老いの自覚は、「自己」というある種の「定常状態」の行き着く先が「自己」の崩壊であるということの自覚、自分が下り坂、梯子の降りる側にいるということの自覚なのであって、その不可逆な過程の先にあるものこそ「死」なのであり、それゆえに「告別」は悲劇的なものになるのだという常識的な見方の方が、告別の悲劇性の拠って来るところを正しく捉えているのではなかろうか?
* * *
おまけとして、当該の節のタイトルの末尾に付加された「短い出会い」についてはどうか?『大地の歌』の「告別」について言えば、確かにそこでの告別は、短い出会いにおいて為されているように見える。一緒にいるわけではない友人に別れを告げるために、わざわざ出会いが設定されるという構図は、だから『大地の歌』でも成立していることになる。だが、その内実はここでジャンケレヴィッチの言う通りだろうか?「告別」のテキストが、マーラー自身が2つの詩を継ぎ合わせたものであることにまず注意しよう。ベトゲの元の詩のみならず、さらにベトゲのNachdichtungの典拠である王維と孟浩然の詩もまた、「告別」の設定そのものでなくて、なおかつそちらであればそれぞれにジャンケレヴィッチ風の「短い出会い」が適用できたかも知れない。だが、マーラーの作品のテキスト自体はどうか?ここで思い浮かぶのは、友人に関するドゥルーズ=ガタリの奇妙なコメントだろう。寧ろドゥルーズ=ガタリの方が、マーラーが「告別」の楽章に施した錯綜とした操作の帰結を捉えている可能性すらあるだろう。更に言えば、元々の孟浩然の詩、王維の詩の「別れ」は「死別」なのだろうか?「別れ」のための「短い出会い」については認めたとして、それはジャンケレヴィッチがこの節で述べているような「死」を前にしたものだったのだろうか?そしてそれとは別に、ベトゥゲのNachdichtungを素材に更に編集を施したマーラーの歌詞においてはどうなのか?
勿論、そこに死の影を見ず、それをマーラーの受けた診断は誤診だったし、マーラー自身も健康そのものであったということを論拠に通説を批難する近年の論調は、ジャンケレヴィッチ風には、マーラー自身の第一人称的な≪感得≫を蔑ろにしていて、それが「客観的」に「事実」に基づいていることを認めたとして、マーラーその人とその作品について語る時にそのことがどこまで意味を持つかについては甚だ疑問だろう。何しろマーラーは『大地の歌』を聴いた人間が自殺をするのでは、とさえ言ったらしいではないか?それともこのアネクドットにしても、弟子が「神話」を創作するために脚色したフィクションであるという証拠でもあるのだろうか?そもそも第一人称的な死を仮に措いたとして、幼少期から兄弟の早逝に繰り返し直面し、その後も兄弟や友人の自殺にも遭遇しているし、余りに有名な長女の死についてのアルマの証言に偽りが含まれているとして、それがマーラー本人にとって耐え難い経験であったことは想像に難くない。所謂「誤診」以前にも、まさにそのキャリアのピークにおいて痔による大量出血が原因で瀕死の状態を経験していて、別にそれを題材とした標題音楽を作曲しなかったからといって、そのことがその後の彼の人と作品に影響していないとか、大した影響はなかったという論拠にはなり得まい。それゆえ私が通説に疑問を感じるのは、異論のための異論の如きものが依拠するものとは全く無関係な理由によるのであって、このような異論ならば、通説との「あれかこれか」で私が迷うことはなく、通説の方が余程「真実」の近くを射貫ていると考える。だがそれもまた程度の問題で、比較をした結果に過ぎず、だからといって通説が的を射ているとは考えていないのである。
* * *
ここでこの読解の当初の目的を再確認しよう。この読解は、ジャンケレヴィッチの『死』の「老化」の章と「別れ」の節の読解を通して、必ずしもジャンケレヴィッチの思索を継承・展開するかたちではなく、寧ろ反面教師としてであれ、マーラーと「老い」の関係についての視座を獲得することを目的としていた。そして実際に、大著の別々の箇所(「老化」は「死のこちら側」、「別れ」は「死の瞬間」に位置づけられていた)に存在する両者の読解を通して確認できたこととして、以下の点が挙げられるように思う。
一見したところ「老化」についての考察は、「別れ」に関する部分での『大地の歌』への参照とは一見して無関係であるように見えるし、「老化」と「死」との区別を指摘していることから、『大地の歌』の参照に関して言えば。従来の「死」と結び付けて捉える通説と共通した発想(アドルノが批判した、第9交響曲の解説における「死が私を語ること」という後付けの標題の類のそれ)の一例として扱うことさえできるかも知れない。一方で、「老化」についての叙述は、一方では「死」についてのものとされる叙述と入り混じってしばしば区別ができず、寧ろそれは端的に「老化」についてのものとして区別するのが妥当に思われる箇所を含み、他方では「老化」が主題である筈の箇所で≪感得≫について語る時、実際には「老化」固有のそれではなく、「死」について語ったことを繰り返すことしかしていないといった箇所もあり、総じて「老化」を「死」から引き離そうとしつつも、その試みは不十分にしか達成されていない一方で、「死」についての叙述の中には、本来「老化」についてのものでしかないものが密輸されているように見える。「死」について斯くも饒舌たろうとし、実際に饒舌である一方で、この著作が『死』についてのものであるという前提を踏まえてなお、西洋の思考は「老化」について、それを正面から取り上げることを避けるというボーヴォワールの批判は当たっていると言わざるを得ないように感じられたというのは偽らざる感想である。
翻って『大地の歌』の「別れ」について言えば、それが「死」の観点からのみ論じられるのは適切でないとしても、それでは「老い」の観点から論じるのは妥当なのかは独立の問題であろう。「死」でも「老い」でもなく、端的に「別れ」そのものであって何故いけないのか?歌詞は素材に過ぎず、作者の心理の投影を安直に作品に対してするべきでないとしたら、「老い」を持ち込むこともまた、人と作品に関する既成の発想に捉われたものではないのかという問いには、別に答える必要があるだろう。だが、ここでは一旦論証抜きで見通しだけ述べれば、「老い」を持ち込むのは心理学的な作者ー作品観に基づく密輸などではない。歌詞は素材だろうが、作品の一部であるには違いなく、あたかも歌詞など存在しないかの如く『大地の歌』を受容するのは(そうした姿勢を全面的に拒否しないまでも)妥当とは言えないとするならば、そして標題的・描写的な形態ではないにせよ、歌詞内容に触発されて作品が生成したのであれば、そこには「生の有限性」の認識があり、「疲労」の感受があり、「老い」の認識があることは明らかなことではなかろうか。「疲労」は「眠り」を誘うのだが、ここでの「疲労」は、ではそれによって「疲労」からの恢復が達成されるような類のものなのか?若き日の回想を呼び起こすようなその「疲労」は寧ろ、生体のロバストネスの変移としてのホメオスタシスの定常位置の変化としての「老い」の感受そのものなのではないか?ジャンケレヴィッチの「老い」の捉え方も、ダマシオの言う中核意識ー中核自己のレベルではなく、従って現象学的には単なる意識の中断を乗り越えた想起や予期が可能な第二次把持のレベルを前提とはしても、それに留まるレベルではなく、スティグレールやユク・ホイの第三次把持のレベルに対応する延長意識ー自伝的自己のレベルに関わるとする把握に通じており、システム論的な「ロバストネスの変移と崩壊」に通じている側面を見出すことができたし、「老い」を外側から観察できる事象としてのみ捉えるのではなく、主観的な認識を必須とする立場は正当なものであるが、そうした点を踏まえた時、『大地の歌』の「別れ」は「老い」の認識に立ったそれであるという把握には一定の妥当性があると主張しうるという見通しは、ここでの読解・検討を通じて確保できたのではないかと考える。
(2023.1.30初稿公開, 2.3更新, 2024.12.18 備忘:マーラーの音楽における「老い」についての論考に向けての準備作業の一部として再編集。改題の上再公開。2025.1.31, 2.2 誤記修正・表現の調整を行い更新。)