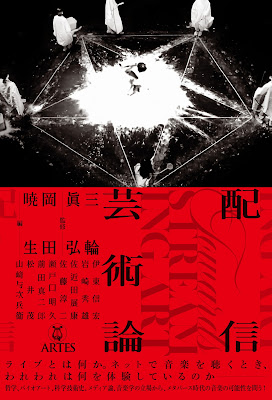丸山桂介「隠れたる神 第九交響曲の「アダージョ」に寄せて」(in 「音楽の手帖 マーラー」(青土社, 1980))より
(…)
マーラーの音楽、なかでもとりわけ第九終章の「アダージョ」を聴いていると、
ときに私は自分の存在の無限のはかなさを感じる。
そこでは生の意味が徹底的に懐疑され、
ほとんど耐え難いほどの世界苦にマーラーの魂が呻吟しているのが余りにもはっきりと私に伝わってくるからである。
彼の苦悩する精神の現実が私の内に浸透し、私をゆり動かし、共苦させるのである。
マーラーの音楽が、日本のこの現実に生きる私達にも深い感動を呼びおこすのは、
孤独な魂の叫びが私達の存在の基盤をゆさぶるからではないだろうか。
十九世紀末の時代精神に根をおろしたマーラーの芸術は、
その意味では時空を超えているといえるかもしれないが、
私にはしかし彼の音楽ははるかに遠く、歴史的時空との関わりを超越したところに立っているように思われる。
この歴史的現実を超越することによって、かえって私達の現実にもあてはまる存在の懐疑を彼の音楽は私達にもたらすのである。
(…)
マーラーの作品はつまるところ音響態でしかないかもしれないが、しかしその音の響きを背後から支えているこのような
彼の創造理念が私達にも感動を与えるのだといえるだろう。クーベリークも来日時に、第九は終章にさしかかるとそれまでの暗雲が
切れて突然のように青空が拡がり、天使が舞い降りてくるといっていた。もちろんマーラーの音楽を聴くのに天使はいらない
といえばそれまでだろう。日本では、あるいはそのような受け取り方がなされていることの方が多いかもしれない。
だが芸術においては、その人間が信じているものは表われるのだ。或る人間が捉え、理解し、自分のものとして身につけているものが表われる。
(…)
既にニーチェが指摘しているのであれば、マーラーの時代にも彼を取り囲んでいたのは神の殺害者であったといえるだろう。
そのなかにあって、彼は神を探し求めた人間のひとりであった。
もちろんルターやバッハにおける隠れたる神と、マーラーにおけるそれとは意味を異にしてはいただろう。
それに実際にヨーロッパの歴史を通じて、キリスト教とユダヤ教がどのような関係にあったのか私には詳らかでないし、
おそらくマーラーにあっても、ニーチェと同様神は超越者一般を指してはいただろう。
ニーチェの「ツァラトゥストラ」の「酔歌」とマーラーの音楽における明るみの、
不思議なほどに一致する感覚の質がそのことを何よりもよく証しているように思われる。
だがそれにもかかわらず「ヨーロッパ文化への入場券」を買うものは、隠れたる神を探したものの仲間に加わらざるを得ないのだ。
何となれば、おそらくはヨーロッパなるものの本源はそこにしかないからなのだ。
しかも神を探すものは、しばしば周囲から嘲けりを受ける運命にあるようにみえる。
マーラーもまた超越者に関わることによって、社会的にも叩きのめされたのではないか。
仕事のうえでのまさつは、彼がユダヤ人だったからであると同時に、
彼が超越者との関わりを芸術の領域に持ちこんで、
周囲の人間には容易に見えない高邁な理念にしたがってことを運ぼうとしたからである。
マーラー自身は、たしかに隠れたる神としての意識をそれほど明確には持っていなかったように思われるけれども、
結局彼もヨーロッパの根源に掉さすことによって、究極的には神の不在の問題に還元されることになる、
人間の生への深い反省や死との対峙を余儀なくされたのである。
彼も本質的に何かを求め探していた人間だったのだ。
だからこそときに烈しく叩きのめされながらも、いや、かえってその故に、
苦難の最中に数々の作品を創造し得たのではなかったのだろうか。
マーラーの「アダージョ」のような作品には、温かい明るみが満ちていると同時に、
私にはまた一方でそこにはしんしんとした孤独が介在しているように思われる。
物狂いの人にのみつきまとっている、これは存在の孤独とでもいったらよいものだろう。
たしかに私達の多くは神の不在にも、神の存在にも関わりをもたない幸福な生活を営んでいるようにみえる。
だがそのような、いわば生なき生の最中にあっても、
マーラーの音楽は突然のように私達に人間の何であるかを開示してみせるようだ。
私達はそれ故に感動し、またそこに社会的疎外感などが加わることによって、
感動はいっそうその振幅をおおきくするのである。
けれども、私達は、というより私はというべきかもしれないが、
その感動を感動として、つまり現実の生活から切り離された次元において、
芸術の鑑賞領域における感動として受け止めているが故に幸福な生活が送れるのかもしれないのだ。
もしマーラーの音楽に真に感動したならば、その人はおそらく何かを探しはじめるだろう。
そしていまの私には、決して不可能であるとはいわないまでも、
そうした何かを探求しつつ生きる生活は、当面日本の現実と決定的に相容れないもののように思われるのである。
丸山桂介の上記の文章に出会ったのは、今から35年前に、音楽の手帖「マーラー」(青土社, 1980)に
掲載されているのを読んだときのことであるが、私見では、日本語で書かれたマーラーを巡る文章の中でも
群を抜いて、圧倒的で永続的な印象を与えられた文章であり、今尚読み直しても、その内容は聊かも古びて
いないと思われる。バッハとベートーヴェンの研究者として知られる著者がマーラーを扱ったという点で、
マーラーの文脈ではマージナルな存在かも知れないが、時代を隔てて日本でマーラーを尚、聴くことの意義を
示しているという点では際立った内容だと思う。
その内容をきちんと受け止めて、それに相応しい文章を書くだけの余裕が、残念ながら今の自分には
無いのだが、最小限の応答として、その内容について若干のコメントを記して後日に備えたい。
著者は「彼の音楽ははるかに遠く、歴史的時空との関わりを超越したところに
立っているように思われる。」と述べているが、これは「隠れたる神」が
問題になりうる意識様態の構造というのが、ある特定の文化的・社会的文脈の
更に特定の時点の環境に依存したものではないという点では正しいが、
にも関わらず、権利上、如何なる歴史的時空との関わりを超越したものである
という意味合いではありえないだろう。
時間を超えることは端的に不可能であって、作曲者の死後も生き永らえている
マーラーの音楽とて、時間を通って存続し続けることで辛うじて永遠に漸近すると
言いうるに過ぎない。それは社会的・文化的な場の歴史的連続性を超えて、
(恐らくは幾分の誤解とともに)1世紀後の極東の島国で受容されているが、
それが、ジェインズ的な意識の考古学におけるホメロス以前の意識の構造にまで
及ぶものなのか、あるいはカーツワイルのような特異点論者の主張する特異点の
向こう側にまで及ぶものなのかは、自明なこととは言えないだろう。
進化生物学的な意識の発達史、あるいはジェインズ的な意識の考古学と、
カーツワイルのような特異点論者の主張する特異点の向こう側の
両方を収めた展望の下では、「隠れたる神」の問題はやはり、
それ自体歴史的な存在である、ある種の意識様態に固有の問題であろうし、
最も外延を広くとっても、遺伝子の搬体としての生物個体の中で
自伝的自己を伴う自己意識を備えた者に固有の問題であろう。
超越性というのは、そうした存在様態固有の認知パターンなのだし、
そうした認知パターンにおいてのみ「隠れたる神」が問題になりうるのだ。
(ただし必要条件であって、十分条件ではないが。)
神を探すことが成立するためには、単に自伝的自己を伴う自己意識を
備えているだけではなく、そうした構造を把握し、境界に身を置かなくては
ならないのだろう。カントのいう、アンチノミーに悩むことを宿命づけられている
「理性」が必要なのであり、そうした「理性」が生じるような場所でのみ、
「隠れたる神」が問題になりうるのだ。
勿論それは、西欧固有のものに過ぎず、極東の島国ではア・プリオリに
禁じられているというわけではない。例えば北村透谷が1世紀前、(奇しくも彼の生涯は
マーラーのそれにすっぽりと覆われてしまっていて、なおかつお互いに因果的な過去・
未来に住んでおらず、知り合うことがないという意味において、
本来の意味での「同時性」が成立しているのだが)マーラーの同時代の
日本に生き、やはり或る意味において「ヨーロッパ文化への入場券」を買い、
当時の日本にあっては(もしかしたら、現代の日本においても未だなお)
例外的な出来事であったかも知れないが、彼なりの展望において「隠れたる神」を
探し求めたことが思い浮かぶ。
「もしマーラーの音楽に真に感動したならば、その人はおそらく何かを
探しはじめるだろう。」というのは全くその通りだと思う。
だが何かを探求しつつ生きる生活の不可能性は、
「当面日本の現実」と「決定的に相容れない」だけでなく、
常に既に、何時の時代の何処の文化的環境においてもそうではないのか?
また、マーラーがユダヤ人であったことは、リーの指摘するように、
彼が西欧の社会における「マージナル・マン」であるための原因の一つで
あるだろうし、具体的なその様態を捨象することは
(ここで問題になっているのが音楽作品という感性的なオブジェクトで
あることを考えれば特に)できないだろうが、にも関わらず、
唯一の原因ではないし、従って「隠れたる神」の探究に至る唯一の
原因ではないだろう。
寧ろ、マーラーの音楽が鳴り響く文化的環境に生を享け、
ふとした偶然からある日マーラーの音楽を聴いた子供は、その「出来事」を介して、
「隠れたる神」の探究に誘われるのであり、それは恐らく、
自伝的自己を伴う自己意識を備えている存在(それには全ての「ヒト」が
含まれるわけではないかも知れないし、逆に「ヒト」以外の存在が
そこに含まれえないと決めつけることもまた、できないだろう)であれば
潜在的に持ちうる可能性であり、それが現勢化するかどうかは、
「出来事」の到来という偶発時にかかっているのだし、逆に一旦
そうした「出来事」が到来してしまえば後戻りはできないのだろう。
著者は「しょせんは音響態に過ぎないかもしれない」としても「芸術」に
おいて、「或る人間が捉え、理解し、自分のものとして身につけているものが
表れる」と述べているが、これも全くその通りだろう。ただしその如何にしてを
考えたとき、それは作品の素材に過ぎない標題性などとは別の水準で可能になって
いることには留意すべきであろう。作品は(マーラー自身、晩年に妻に対して
書いたように)「抜け殻」に過ぎないだろうし、「出来事」の経験についていえば、
その痕跡に過ぎないだろう。だが一回性で反復不可能な到来としての「出来事」は
その痕跡であるところの「作品」なくしては、記憶され、想起され、
反復され、継承されえないのだ。「出来事」の主体の有限性を超えて、
死後の生命を獲得することはできないのである。
作品は活動プロセスの痕跡であり、その定着には記号化・離散化・
デジタル化が不可避である。化石がそうであるように、響きそのものではなく、
響きのパターンが記録される。それは「抜け殻」(マーラー)かもしれないが、
自己を超えて生き延びることとは、そのようにしか可能ではない。
見方を変えれば、そうすることによって生物個体としての有限性を
超えて、遺伝子の複製とは異なった水準での、個体の記憶の継承、一回性の
「出来事」の記憶の継承という「反逆」(ダマシオ『自己が心にやってくる 意識ある脳の構築』)が
可能になるのだ。それは「抜け殻」であると同時に、(マーラーが、これはゲーテの
「ファウスト」第1部の地霊の台詞を引用して述べるように)「神の衣」でもあるのだ。
我知らずして、いわば盲目的に神の衣を織るためには、自伝的自己を
伴う自己意識は必ずしも必要ない。だがある価値にコミットして、
己の出遭った価値あるものの(漸近的な)永続化をめがけ、
そうした出遭いという一回性の出来事を記憶し、出来事の一回性を超え、
自己の有限性をも超え、他者に向けて継承することを目指して、
作品としてデジタル化する意図をもって「衣を織る」ことは、
自伝的自己を伴う自己意識なしには為し得ない。
そして、そのことを「作品」を聴くことによって感じ取るのもまた、
自伝的自己を伴う自己意識なしには為し得ないだろう。否、実際には、
マーラーの音楽を聴くという経験が、意識がある様態を持つように自己
形成することに寄与している筈なのであって、それ自体が或る種の
文化的複製子(ミーム)なのである。自伝的自己を伴う自己意識が
取りうる或る種の意識の様態、超越性、外部からの到来に対する応答と
いった出来事が生じるような様態を伝播させる搬体がマーラーの
音楽作品という文化的複製子だ、というわけである。
それはある種の
共進化の如きものとして捉えることができるのかも知れないが、
それよりも私にとって興味深いのは、マーラーの作品の構造が持つ、
意識の様態との構造的な類似性である。マーラーの音楽は、ある種の
意識の様態を別の素材を用いて物質化して定着させたかの如くであり、
それ自体は「生きて」はいなくとも、生がどのような構造を備えて
いるかは、それによって推測できるような構造物であり、その限りで
カールハインツ・シュトックハウゼンが、宇宙人が「人間」のことを
知ろうと思ったら、マーラーの音楽を調べれば良いといったのは
(勿論、その「人間」は、生物学的な意味でのヒトのことではなく、
広くとってもジェインズのいうヒュポスタシス以降、カーツワイルの
特異点以前のエポックの、自伝的自己を備えた意識を持つ存在という
ことになろうが)、それなりに正しい直感に基づく発言なのではと思われる。
マーラーの音楽は、優れて「意識の音楽」であり、マーラーの音楽自体が、
自伝的自己を伴う自己意識の「時代」を証言し、その構造を映し出し、
その宿命を示唆する存在、つまり自伝的自己を伴う自己意識の自己認識の
結果であり、尚且つ、そうしたマーラーの音楽を聴き、それによって自己を
形成し、その上でそれについて証言することは、そうしたマーラーの音楽に
対するコミットメントとしての行為遂行性を帯びており、それは自伝的自己を
伴う自己意識の自己の宿命に対する或る種の「反逆」に対するコミットメント
でもあるのだ。
それをマーラー音楽というミームの詭計と捉えることも
できるだろうし、そうした見方にも一部の理はあるだろうが、もしそうであると
するならば、更に一歩進んで、マーラーがこのような音楽を創造したこと自体もまた、
或る種の宿命であり、仕組まれたものなのだということになるだろう。著者の言うように、
マーラー自身が「来たれ」という呼びかけに応答すべく、作品を創造したのだが、
今度はその(作曲者が、ではなくて)作品自体が、聴き手に対して「来たれ」と
誘うことになる。
ここで、シェーンベルクのプラハ講演における第9交響曲に関する
コメントを想起してもいいだろう。曰く、作曲者はメガホンに過ぎず、その背後に
真の主体が居るといった見方は、まさにここで問題になっているような構造を
言い当てたものに違いない。その主体はまた、第8交響曲の2つの「来たれ」の
命令を発した存在なのだが、それは一体誰なのか。
進化論についての論争でもそうであるように、そうした詭計を仕組む者を
「神」と呼ぶ立場もあろうし、「隠れたる神」がそうであるように、寧ろそうした
立場こそが伝統的、正統的な立場なのであろう。だが今日であれば、それは或る種の
自己組織化の結果、創発的な現象と見做すべきではなかろうか。マーラーの音楽を
19世紀末の西欧という、歴史的・文化的環境に還元して理解するのではない、別の可能性がここには
開けているように思われる。「神」や「天使」という語彙ではなく、だが、
超越を、出来事の到来を語る別の語彙が必要なのではなかろうか。
神を殺すのではなく、その後の時代に相応しい「隠れたる神」を探す別の仕方が
ここでは問題になっているのだ。ドイッチュの言う「無限の探究」もまた、
そのような試みの一つなのだと私には思われる。
神経科学の発達で脳のメカニズムが少しずつ解き明かされ、
意識についての語り方が変わりつつある今、それは、別の仕方で説明し直されることを
求めているのではなかろうか。そしてそれは、まずもってマーラーの音楽を
狭義の音楽学の語彙によってではなく、或る種のシステムとして捉えること、
狭義の美学の語彙によってではなく、情報の観点から捉えることによって可能に
なるのではなかろうか。そしてそれはマーラーの音楽を、それ自身そのように
志向していたように、狭義での「芸術」の閉域の境界において考えることを
求めているのではなかろうか。マーラーの音楽はベイトソンの言う
「無意識のエクササイズ」なのであり、超越的なものへの開け、出来事の到来を
記録したアーカイブであり、カーツワイルの言う特異点の手前に居る人間にとって、
差し当たり特異点に達するまでの間は少なくとも意義を持つものに違いないのだから。
(2015.4.22/24)